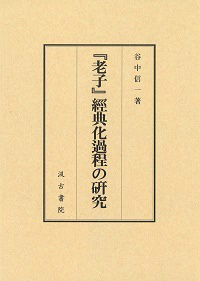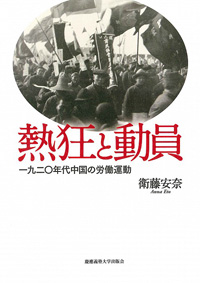日韓近期漢學出版物(十五)
7、日本·モンゴル關系の近現代を探る:宗教復興后を生きぬくボン教徒の人類學的研究
時 間:2015年8月
作 者:ボルジギン·フスレ 著
出版單位:東京:風響社
內容簡介:
モンゴル國の國連加盟(G. ミャグマルサムボー)
モンゴルの國連加盟における臺灣政権の対応(ボルジギン·フスレ)
1910年代フルンボイル地域における日本人社會(ソルヤー)
1925年の満鐵外モンゴル調査隊拘束事件とモンゴル人民共和國(青木雅浩)
日本人の対モンゴル観,モンゴル人の対日本観:調査データからの検討(湊邦生)
20世紀初期における日本とモンゴルの文化交流:ロブサンチョイドンを事例に(シバウチン·チョロモン)
現代モンゴル人の外國人観の一考察:B.リンチェン『曙光』を題材として(池部尊則)
モンゴルをめぐる日本と中國の外交戦略:ポスト冷戦時代を中心に(泉田浩子)
1990年代前期モンゴルにおける歴史教育実踐:O教師のライフヒストリーにみる教師観·歴史観の形成(髙橋梢)
モンゴルの教員養成課程への授業研究關連科目導入の意義(ノルジン·ドラムジャブ)
日本とモンゴルにおける,教育の國際化に關する考察(井場麻美)
內モンゴル東部地域における教育の一考察:ホルチン左翼后旗を中心として(ボヤント)
8、留學生の早稲田:近代日本の知の接觸領域
時 間:2015年12月
作 者:李成市、劉杰 編著
出版單位:東京:早稻田大學出版會
內容簡介:
序章 留學生の早稲田大學(李成市)
第1節 本書のねらい
第2節 本書の成り立ち
第3節 本書の構成
第1章 戦前期早稲田大學のアジア人留學生の軌跡——中國人と臺灣人留學生數の動向を中心に(紀旭峰)
第1節 東京専門學校から早稲田大學へ
第2節 中國人と臺灣人留學生の実態
第3節 留學生·知識人の出會いの場としての早稲田
第2章 危機の時代における早稲田留學——中國人留學生譚覚真の軌跡(島田大輔)
第1節 早稲田大學入學までの軌跡——郷里での修學と最初の留學:一九〇九~一九三一年
第2節 早稲田大學時代——一九三一年四月~一九三四年三月
第3節 卒業后の軌跡(1)外交官時代の譚覚真:一九三四~一九四四年
第4節 卒業后の軌跡(2)戦后期の譚覚真:一九四五~二〇〇一年
第3章 臺灣自治の指導者「楊肇嘉」と早稲田——學問と政治の融合が生み出す自律的思考(野口真広)
第1節 生い立ちと在地社會での位置
第2節 一九二〇年の地方制度改革の影響
第3節 早稲田大學入學と政治運動
第4章 李相佰、帝國を生きた植民地人——早稲田という「接觸領域」に著目して(裵姈美)
第1節 早稲田大學に學んだ朝鮮人留學生
第2節 李相佰Ⅰ:「東洋史」研究者として
第3節 李相佰Ⅱ:帝國のスポーツ人として
第5章 早稲田大學野球部と朝鮮——近代日朝スポーツ交流史の斷面(小野容照)
第1節 日本野球史上の早稲田大學野球部
第2節 朝鮮における野球の発展と早大野球部
第3節 植民地朝鮮の野球界と早大野球部
終章 早稲田はアジアの大學だった(劉杰)
第1節 共創する「早稲田文化」
第2節 留學生とアジアの早稲田
第3節 「主體性」を貫く留學生たち
9、『老子』經典化過程の研究
時 間:2015年12月
作 者:谷中信一 著
出版單位:東京:汲古書院
內容簡介:
序
第一章 郭店楚簡『老子』考
第二章 郭店楚簡『太一生水』 考
第三章 上博楚簡(七)『凡物流形』考
第四章 上博楚簡(三)『恒先』考
第五章 『莊子』天下篇考
第六章 いわゆる黃帝言考
第七章 『淮南子』道應訓所引『老子』考
第八章 『史記』老子傳に隱された眞實
第九章 北大漢簡『老子』の學術價値―「執一」概念を中心に
終章
10、熱狂と動員:一九二〇年代中國の労働運動
時 間:2015年12月
作 者:衛藤安奈 著
出版單位:東京:慶應義塾大學出版會
內容簡介:
序章
1 社會現象としての中國労働運動
2 中國労働運動史をめぐる研究史
3 広東·上海·武漢における労働運動の特征
4 一次史料と二次史料の扱いについて
5 本書の構成
第一章 熱狂する社會——本書の視點
1 熱狂する社會について——大眾社會論の問題意識
2 孤立した集団
3 「孤立した集団」をめぐる議論への視點の追加——イデオロギーとジェンダー
4 本書の仮說
第二章 広東の動員裝置
1 広東労働者をめぐる諸環境
2 広東における國共両黨の黨組織——一九二〇~二七年
3 広東における國共両黨の労働者組織——一九二一~二六年
第三章 黨による広東労働者の動員
1 動員技術としての「ストライキ」——一九二二年
2 政府軍傭兵部隊としての糾察隊——一九二四年
3 混沌と紛爭の拡大——一九二五~二六年
第四章 上海の動員裝置
1 上海労働者をめぐる諸環境
2 上海における國共両黨の黨組織——一九二〇~二七年
3 上海における國共両黨の労働者組織——一九二四~二七年
第五章 黨による上海労働者の動員
1 黨による動員の「失敗」——一九二二年
2 失業工頭と「打廠」戦術——一九二五年二月
3 混沌と紛爭の拡大——一九二五年五月以降
第六章 武漢の動員裝置
1 武漢労働者をめぐる諸環境
2 武漢における國共両黨の黨組織——一九二〇~二七年
3 武漢における國共両黨の労働者組織——一九二二~二七年
第七章 黨による武漢労働者の動員
1 內陸の労働運動と黨の接觸——一九二二~二三年
2 黨による再動員と蕭耀南政権の弾圧——一九二五年六月
3 混沌と紛爭の拡大——一九二六~二七年
終章
1 三地域の共通點
2 三地域の相違點
3 結論——政治的含意と現代中國への展望
11、中國女子労働者の階級と消費空間
時 間:2015年11月
作 者:陳蕭蕭 著
出版單位:龍ケ崎市:流通経済大學出版會
內容簡介:
序章
第Ⅰ部 価値実現空間の生產と消費者化
第1章 消費観の変化?──否定から肯定、さらに推奨へ
第2章 価値生產空間
第3章 価値実現空間と消費者化
第Ⅱ部 利用者の社會階級と二類型の商業施設
第4章 OLと女工の階級分化
第5章 OL階級と女工階級の消費空間
第6章 社會階級と消費空間
第Ⅲ部 女工の體験空間
第7章 「幸福な消費生活」空間
第8章 女工階級の愈し空間
第9章 ユーザーによって生きられる空間
終章
12、戦后日中交流年志1945-1972(一套17卷)
時 間:2015年11月起陸續出版
作 者:大澤武司 解說
出版單位:東京:ゆまに書房
內容簡介:
戦后から國交正常化に至る國交のない約28年間の日中間の交流概況と詳細な日中交流年表。これに加え、重要協議や取決め、聲明文など全文を記載するとともに人的交流や日中貿易の狀況等を詳細に記録する戦后日中關系史必備の基礎數據。
【底 本】
第1巻『戦后の中共年志』內閣官房內閣調査室編纂(推定、記載無し)
第2巻?第5巻『日本·中共交流年志』內閣官房內閣調査室編纂(第3巻?第5巻は推定、記載無し)
第6巻?第17巻『日本·中共(中國)交流年志』社団法人民主主義研究會編纂