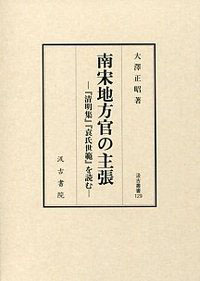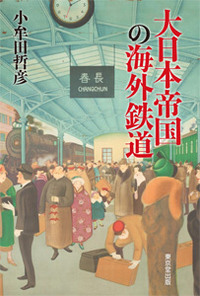日韓近期漢學出版物(十五)
13、近代中國における知識人·メディア·ナショナリズム:鄒韜奮と生活書店をめぐって
時 間:2015年11月
作 者:楊韜 著
出版單位:東京:汲古書院
內容簡介:
第一部 導入篇
序章 生活書店及び鄒韜奮研究
第一章 近代中國(上海)のジャーナリズム環境
第二部 人物篇:生活書店の知識人たち
第二章 ジャーナリスト鄒韜奮の発展
第三章 戦時中國における鄒韜奮の政治活動
第四章 生活書店の人々:黃炎培·杜重遠·胡愈之·徐伯昕を中心に
第三部 書店篇:近代出版メディアの一つのあり方
第五章 生活書店の募金活動
第六章 戦時下の経営管理
第四部 言說篇:メディアとナショナリズムの交錯
第七章 メディア化された共同體:生活書店出版物の投書欄
第八章 事例分析:投書欄における「戀愛と貞操」をめぐる論爭
第九章 新生事件からみる日中メディア間の対抗
第十章 「國貨」をめぐる言說の浸透性検證
終章 生活書店から三聯書店、そして再び生活書店へ
14、南宋地方官の主張:『清明集』『袁氏世范』を読む
時 間:2015年11月
作 者:大澤正昭 著
出版單位:東京:汲古書院
內容簡介:
第一部 『名公書判清明集』の世界
第一章 『清明集』の世界へ——定量分析の試み
一 『清明集』の全體像
二 地名の分析
三 人名の分析
四 その他の要素の分析
第二章 胡石璧の「人情」——『清明集』定性分析の試み
一 「人情」論爭
二 胡石璧の判語における「天理」「義」「疾悪」
三 胡石璧の「人情」
四 蔡久軒の「天理」と「人情」
第三章 劉后村の判語——『清明集』と『后村先生大全集』
一 判語作成の時期
二 判語の書式上の特征
三 劉后村の判斷基準
第四章 南宋判語にみる在地有力者、豪民
一 先行學說と史料研究
二 南宋時代の判語に見える在地有力者
三 「豪民」の特征的活動
補論 中國社會史研究と『清明集』
第二部 『袁氏世范』の世界
第五章 『袁氏世范』の研究史と內容構成
一 研究史と課題の設定
二 『世范』の全體構成
第六章 『袁氏世范』の世界
一 『世范』著述のねらい
二 『世范』の世界
第七章 袁采の現実主義——『袁氏世范』分析への視點
一 『世范』の用語からみる論理構造
二 『世范』の理念と現実認識
第八章 宋代士大夫の「興盛之家」防衛策
一 中國史上の家について
二 家の存続
三 袁采の教訓
おわりに——防衛策の効果
15、大日本帝國の海外鐵道
時 間:2015年11月
作 者:小牟田哲彥 著
出版單位:東京:東京堂
內容簡介:
概說 外地に關する基礎知識
第1章 臺灣の鐵道旅行
1 臺灣の鐵道事情概観
2 日本統治時代の臺灣の観光事情
3 臺灣へのアクセスルート
4 日本統治下にあった臺灣への第一歩
5 臺灣の鐵道旅行とことば
6 臺灣に広がる多彩な鐵道網
6 臺灣島を走った名物列車
8 臺灣を上手に旅するトクトクきっぷ
第2章 朝鮮の鐵道旅行
1 朝鮮の鐵道事情概観
2 日本統治時代の朝鮮の観光事情
3 朝鮮へのアクセスルート
4 朝鮮の出入域事情
5 當初は混在した內地との時差
6 朝鮮旅行での両替事情
7 朝鮮の鐵道旅行とことば
8 朝鮮各地の多彩な鐵道路線
9 朝鮮を駆け抜ける廣告牌列車
10 朝鮮を上手に旅するトクトクきっぷ
11 朝鮮の鐵道名所を訪ねる
第3章 關東州の鐵道旅行
1 關東州の鐵道事情概観
2 關東州へのアクセスルート
3 關東州を旅するテクニック
4 關東州の鐵道路線
第4章 満洲の鐵道旅行
1 満洲の鐵道事情概観
2 満洲の観光事情
3 旅行時の治安について
4 満洲へのアクセスルート
5 パスポートがいらない外國·満洲
6 同じホームで并ぶ列車に時差がある
7 鐵道旅行者は復數の暦を使い分けよう
8 統一通貨がない満洲國以前の両替技術
9 満洲の鐵道旅行とことば
10 満洲開拓と歐亜連絡を擔う、満洲の各路線
11 萬里の長城を越えた日本の鐵道路線
12 満洲の大地を走る名物列車
13 満洲を上手に旅するトクトクきっぷ
14 満洲の鐵道名所を訪ねる 第5章 樺太の鐵道旅行
1 樺太の鐵道事情概観
2 樺太へのアクセスルート
3 樺太を旅するテクニック
4 樺太の鐵道名所ガイド
第6章 南洋群島の鐵道旅行
1 知られざる南洋群島の鐵道
2 南洋群島の旅行案內
3 サイパン·テニアン·ロタの鐵道
4 パラオの鐵道
16、日本思想史研究——中國思想展開の考究
時 間:2015年10月
作 者:加地伸行 著
出版單位:東京:研文出版
內容簡介
第一部 日本古代における中國思想受容
第一章 中國思想の先駆的受容
前方后円墳に投影された経學的意味/邪馬「臺」國/「臺」字の解釈/『太平御覧』所引『魏志倭人伝』について
第二章 中國思想の內面化
空海と中國思想と——『指歸』両序をめぐって/空海の言語論における日本的性格/大真言から小真言へ——『文鏡秘府論』の構成/『竹取物語』と道教と
第二部 儒教の本質的理解——中江藤樹の孝
第一章 『孝経啟蒙』の成立
『孝経』について/日本における『孝経』/『孝経大全』/明人朱鴻『孝経輯録』/『孝経啟蒙』の成立/『孝経』をめぐる藤樹と羅山と
第二章 『孝経啟蒙』諸本の系統とその展開と
諸本の解題/藤樹の孝における孤剣樓本『孝経啟蒙』の意義/天理図書館所蔵本『孝経啟蒙』について/『孝経啟蒙』の文獻的特征と諸本の關系と/真佑本『孝経啟蒙』と安井真佑と
第三章 中江藤樹の孝
藤樹の孝についての川島武宜說批判/川島武宜說批判の補論/藤樹の孝についての守本順一郎說批判/日本陽明學の孝
第三部 中國學の総合的理解
第一章 中井竹山·中井履軒と懐徳堂と
漢詩文/字音/経學/史學/懐徳堂文庫所蔵漢籍研究の予備調査
第二章 皆川淇園と大田錦城と
皆川淇園の『論語繹解』/大田錦城の『論語大疏』·『仁說三書』
第四部 儒教に対する誤解
教育勅語とは何か/丸山真男について
鶏肋二束·上
前方后円墳に投影された中國思想/飛鳥の削られた木簡/井真成は朋友を悼む日本人か/『萬葉集』の「耆矣奴」考/『伊勢物語』「井筒の歌」正解/亀井南冥の『論語語由』/網野善彥氏の「百姓」について/天理教の「九億九萬九千九百九十九人」/懐徳堂から適塾へ
鶏肋二束·下(講演)
泊園書院と懐徳堂——大阪の學問/天理教の「おふでさき」/教育勅語の中の儒教
資料一 『孝経啟蒙』孤剣樓本影印
資料二 孤剣樓本『孝経啟蒙』の前附·『孝経』本文の活字版